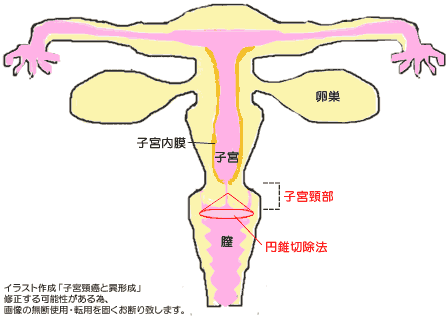子宮がん検査=細胞診
会社の健康診断や一斉に行われる「子宮がん検診」の多くは、「子宮頸部細胞診」です。
子宮体がんは閉経後に起きることがほとんどの為、50歳くらいまでの女性に積極的に行われるのは子宮頸がん検診の細胞診。子宮頸がんに罹患(りかん)する女性は20代・30代を中心に、働き盛りで妊娠や育児中の女性に多く発生しています。日本人女性の死亡率上位に入るほどです。
私が「子宮がん検査(子宮頸部細胞診)」を初めて受けたのは、26歳のときでした。
低容量ピルを服用していたことで、半年に一度の子宮がん検査が必要だったから、という理由でしたが、その1回目の子宮がん検査で私は「擬陽性(ぎようせい)」という告知を受けました。
(子宮体癌の検査を受けたい場合は、「子宮がん検査」と言わずに、婦人科で「子宮体がん検査」と申し出ましょう)
子宮頸部 細胞診(しきゅうけいぶ さいぼうしん)とは
[memo title=”子宮頸部細胞診とは”]「子宮頸がん(しきゅうけいがん)」の発生しやすい部分(子宮頸部粘膜の扁平上皮領域と、円錐上皮領域の境界面)を、綿棒やヘラ、ブラシなどで軽くこすって細胞摂取して、顕微鏡で調べる検査[/memo]
細胞診は一瞬で済み、痛みは全くありません。子宮頸部は痛みを感じにくい部分だからです。
「がん」細胞は正常細胞とは異なる形をしているので、かなり正確に「がん」の危険性をみることができます。短時間で済み痛みもないことから集団検診のスクリーニング検査はこの細胞診を取り入れています。
細胞診は最終診断ではなく、あくまでスクリーニング(仕分け)の検査法ですが、細胞診と子宮頸部組織診の一致率は約95%とほぼリンクしています。
子宮頸がんの発生個所は子宮頸部のここ、とほぼ分かっていますが、検診時のスクリーニング検査の場合、医師が手探りで膣内から採取するために、ごく稀ではあるものの、すぐそばにある異形成や子宮頸がんの細胞にヒットさせることができないケースもあります。
管理人@sarryも経験しましたが、可能であれば、婦人科での細胞診検査を受ける際には、「コルポ診」を併用した細胞診を受けることをおすすめします。
>>
子宮頸部細胞診の結果分類について
「細胞診」で最終診断することはできないので、細胞診の結果は病名ではなく「クラス1から5」までで表します。
- クラス1・・(陰性)正常
- クラス2・・(陰性)炎症などの影響を受けて少し変化した細胞があるが、正常
- クラス3/LSIL・・(擬陽性)軽度から中等度の異形成を疑う
- クラス3b/as-cus(アスカス)・・(擬陽性)高度の異形成を疑う
- クラス4・・(陽性)早期がん、0期のがん細胞を疑う
- クラス5・・(陽性)1a期以上のがん細胞を疑う
[alert title=”注意”]上記は、「細胞診」の結果分類です。子宮頸がんの分類ではありませんので、混同しないようにしてください[/alert]
「細胞診」クラス1、2以外は、「~を疑う」という表現になっているように、細胞診結果「クラス3b」=高度異形成とは限りません。
各分類の説明はあくまで「~を疑う、想定する」ものです。
本当にそうなのか?は、子宮頸部細胞診より詳しい検査である子宮頸部「組織診」を受けて判断します。
精密検査(子宮頸部 組織診・コルポ診)
細胞診で異常があった場合(クラス3a・3b・4・5)、精密検査が必要で「コルポ診」検査と「組織診」検査を行います。
[memo title=”コルポ診と組織診とは”]異形細胞・悪性細胞は肉眼では診断できないのでコルポスコープという拡大鏡で8~40倍に拡大し(コルポ診)、疑わしい部分の組織を採取し(組織診)、標本を作って顕微鏡で診断する方法[/memo]
子宮頸部の疑わしい部分を酢酸を塗布すると病巣が白く染まりはっきりとわかるので、狙いを定めて米粒程の組織を採取します。痛みは殆どなく、出血も間もなく止まります。
細胞診、コルポ診、組織診は通常の外来受診で行えます。
子宮頸部組織診の結果分類について
正常・軽度異形成・中等度異形成・高度異形成・上皮内癌・浸潤癌
軽度異形成~高度異形成・上皮内癌(0期/初期癌)の治療については、『異形成~治療・手術の種類~子宮頸部異形成のあれこれ』をお読みください。
子宮頚癌(上皮内癌~浸潤癌)の治療等については、『「子宮頸がんとは」子宮頸部異形成のあれこれ』をお読みください。
治療を兼ねた病理検査「円錐切除術」
また、さらに詳しく調べる場合に、子宮頸部を円錐状に切り取って組織を詳しく検査する「円錐切除術」を行うこともあります。
「円錐切除術」は治療も兼ねており、検査の結果「がん」や異形成が切り取れていれば治療も終了ということになります。
「円錐切除術」を行う場合は入院が必要で、病院や使用する器具によって日帰り~1週間程度と日数も異なります。
高度異形成の場合、一部に上皮内癌(上皮内がん)が隠れている場合もあるので様子を見て円錐切除で検査・治療することも広く行われています。
子宮頸がん自動判定システムとは
2008年1月23日の日経産業新聞に子宮頚癌判定の新しいシステムについて掲載されていたのでご紹介します。

「子宮頸がん自動判定レーザー」で1時間50人「疑い」選別高精度
医療検査機器大手のシスメックスは、日本で20-30代の女性を中心に増えている「子宮頸がん」を自動的に判定するシステムを開発した。レーザー光で細胞の核の大きさなどを測り、がんかどうか瞬時に判定する。
一時間で50人分に対応でき、医師による顕微鏡検査に比べて検査効率を飛躍的に高められる。原理的にはほかのがんの判定にも応用が可能で、用途拡大を検討している。
システムは前処理装置と判定装置の二台で構成。これまでの医師による検査法と同様に、子宮の入り口近くを医療用の綿棒でこすって採取した組織を使って判定する。
採取した組織は前処理装置にセット。数百個以上の細胞が固まっている組織を複数の試薬と反応させ、細胞を一つ一つバラバラにする。
さらに核に含まれるDNA(デオキシリボ核酸)を染色する。
その後判定装置に移し、内部で細胞を一つずつ落下させ、レーザー光を照射して核の状態を調べる。
がん細胞は増殖力が旺盛なので遺伝情報を記録しているDNAの量が多く、核は正常な細胞より大きく、染色の度合いも強いという。
核の大きさと染色度合いの二つの指標をもとに、がん細胞かどうか判定する。
同社は被験者の同意を得て五百人近くの組織を集め、これらの装置で、がんの疑いが強い人を精度良く選別できることを確認した。前処理と計測の二役をこなす新型装置を開発したうえで、三月から日欧で一万人規模の実証試験を実施する。
専門の医師による顕微鏡検査は、日本で年千二百万件、世界で同一億五千万件が実施されている。
患者数の増加により、先進国でも発展途上国でも自動検査法に対する需要は高まっている。
同社は当面、顕微鏡検査に先駆けたスクリーニング検査の手法として普及させ、実績を積み重ねたうえで将来は確定診断の新手法として当局の認可を得たい考え。
子宮頸がんは体の深部のがんと異なり、がんと疑われる組織を比較的簡単に採取できる。
がんの原因ウイルスの有無を調べる遺伝子検査法も実案化されているが、ウイルス保有者の約95%はがんを発症しないため、がんかどうかの判定には使いにくかった。
このためがんを早期に精度良く発見できる手法の開発が求められていた。
より精度の高い判別システムが導入される日が待ち遠しいですね。
\その他の「異形成に関する記事」はこちら/
[say name=”管理人@sarry(さりぃ)” img=”https://indivi.net/wp-content/uploads/2018/05/iconsmall-1.png”]上記記事を読んでも分からないことがあれば、異形成 専用掲示板 でお尋ねください[/say]